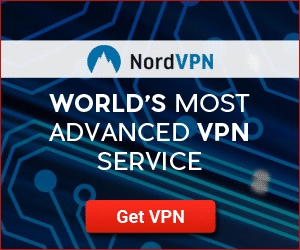Contents
特集:未来を照らす新エネルギー
― 世界初のトリウム原子炉、中国の砂漠に誕生
中国甘粛省の静かな砂漠地帯で、世界が注目すべき出来事が起こった。世界初とされる稼働中の「トリウム原子炉」が、静かに息を吹き返したのだ。しかも、驚くべきことにその技術の大部分は、かつてアメリカで非機密化された研究に基づいている。
トリウム。それは「核エネルギーの聖杯」とも囁かれてきた夢の燃料。従来のウラン原子炉に比べ、遥かに安全で、環境に優しく、兵器転用も困難とされている。5年前、ColdFusionチャンネルはこの理論を紹介したが、今、それが現実になった。
しかし、これは単なる技術革新にとどまらない。公共投資による長期的な研究が、どのように未来を変えるかを示す生きた証でもある。
トリウムの力 ― 想像を超える効率と安全性
わずか5,000トンのトリウムで、地球上のすべてのエネルギー需要を1年間まかなえるとされている。しかも、その多くがすでに存在する採掘廃棄物などから容易に回収可能。ウランよりも約200倍効率的に利用でき、化石燃料と比べると桁違いにクリーンなエネルギー源だ。
この新型原子炉が採用しているのは「溶融塩炉」という形式。燃料は液体状の塩に溶かされ、摂氏約650度で循環する。この方式の最大の利点は、安全性の高さ。もしもトラブルが発生した際には、炉底の「フリーズプラグ」が溶け、重力により燃料が安全な場所へ排出される。メルトダウンの心配もない。
アメリカが築いた基盤、中国が手にした未来
皮肉なことに、中国のこの画期的な成果は、1960年代のアメリカが公開していた研究成果によって実現された。かつてオークリッジ国立研究所で進められていた「溶融塩炉実験(MSRE)」は、実用化寸前にまで達していたにもかかわらず、冷戦下の軍事目的の優先や政治的な判断により、道半ばで打ち切られてしまった。
その遺産を受け継いだのが中国だった。
中国科学院の研究者たちは、膨大な米国の非機密資料を丹念に研究し、再現と改良を重ねた。2009年に国家プロジェクトとして本格始動。数百人の研究者が日夜取り組み、ついに2023年、持続的な核反応を達成。2024年6月には、実際に稼働可能なトリウム炉として運用が開始された。
トリウムとは何か?
― 新時代のエネルギー源の正体に迫る
トリウムは自然界に豊富に存在する放射性元素で、地殻中にはウランの約3倍の量が含まれている。トリウム自体は「核分裂性(フィッサイル)」ではないため、単体では連鎖反応を維持できない。だが、他の物質と反応させることで「ウラン233」という核燃料に変化し、そこから発電が可能になる。
従来のウラン原子炉では、固体燃料と高圧冷却水が用いられるため、安全性や柔軟性に限界があった。これに対し、トリウム炉(特に溶融塩炉)は、液体状の燃料を用い、かつ低圧で運用できるため、設計自体が根本的に安全寄りに進化している。
この違いが、福島第一原発やスリーマイル島事故などの重大事故とは一線を画す「事故が起きにくい原子炉」という評判を生んでいる。
トリウム炉が優れているとされる4つの理由
1. 豊富な資源量
トリウムは採掘しなくても、レアアースの副産物として大量に回収されている。中国には今後2万年間、国内エネルギー需要をまかなえるトリウム埋蔵量があるという。
2. 安全性
トリウムはそのままでは連鎖反応を維持できないため、暴走やメルトダウンのリスクが極めて低い。さらに溶融塩炉では高圧冷却が不要なため、構造上のリスクも小さい。
3. 環境負荷の低さ
トリウムによる核廃棄物は、ウランに比べて放射性物質の半減期が短く、数百年で安全なレベルにまで低下する。温室効果ガスも出さない。
4. 効率の良さ
トリウムはウランに比べて最大200倍のエネルギーを生み出すことが可能。理論上、手のひらサイズのトリウムで一生分の電力をまかなえるとされている。
なぜアメリカはトリウムを捨てたのか?
ここで浮かぶのは当然の疑問――なぜアメリカは、この有望な技術を見捨てたのか?
答えは「政治と軍事の都合」だ。
冷戦下、アメリカはウランとプルトニウムを用いた高速増殖炉を優先した。それは核兵器の材料を素早く大量に製造できるからである。一方、トリウムは兵器転用が難しく、軍事的には価値が薄かった。
また、規制も障壁となった。液体燃料炉の運用は、既存の原子力規制に適合しにくく、1メガワット以上の出力を出すには膨大な許可手続きと費用が必要だった。
そしてなにより、原子力界の主流は「物理学者による固体燃料中心の世界」であり、化学的アプローチである溶融塩炉は主流の理解から外れていた。オークリッジのアルヴィン・ワインバーグ博士が描いた「未来のビジョン」は、結局、理解されずに封印されてしまったのだ。
そして中国がバトンを受け取った
それから数十年後、NASAエンジニアのカーク・ソレンセンが2000年代にこの技術を再発見。アメリカでは関心を集めなかったが、彼の研究に目をつけた国があった――中国だ。
2009年、中国政府は正式に「トリウム溶融塩炉プロジェクト」を始動。2018年には建設が開始され、2023年には持続的核反応を実現。2024年6月、稼働を開始した。
この技術革新の陰には、数百人の研究者が年間300日以上を現地で過ごし、米国の資料を解析しながら、自らの合金「Hastelloy N(耐食性合金)」まで開発するという、壮絶な努力があった。
プロジェクトの責任者はこう語る。
「ウサギが油断すれば、カメが追い越す時が来る。今がその時だった。」
トリウム炉の現実と限界
― 未来のエネルギーは「夢」で終わるのか?
中国が世界で初めてトリウム溶融塩炉の実稼働に成功したとはいえ、この技術が一気に世界中に広まるわけではない。過去、ドイツ・インド・オランダ・アメリカなどもトリウム炉の商用実験を試みたが、1980年代までにすべて中断された。
理由はただ一つ――「コスト」だ。
トリウムを核燃料として利用するには、「抽出」「変換」「再処理」といった複雑な工程が必要で、ウランに比べて高コスト。加えて、長期的な運転には燃料中に蓄積される副生成物の管理が不可欠で、それにも費用と高度な技術が求められる。
安全性や効率に優れているにもかかわらず、商業ベースに乗せるには経済性の壁が立ちはだかっているのが現実だ。
軍事転用ができないという強み、そして弱み
よく言われるのが、「トリウムは兵器転用ができないから冷遇された」という説。実際には、「できない」のではなく「非常にコストがかかる」だけで、理論上は兵器にも転用可能だ。ただ、その非効率さゆえに、軍事国家の関心は薄れたというのが真相に近い。
逆に言えば、それこそがこの技術の平和的価値でもある。兵器には不向き、だが民間エネルギーには革新的。まさに現代の倫理的技術ともいえる。
トリウムの未来は宇宙へ?
トリウムには、さらにもう一つの可能性がある――「宇宙利用」だ。
溶融塩炉は冷却水を必要としないため、乾燥地帯や宇宙空間でも稼働可能。実際、月面には豊富なトリウムが存在することが観測されており、将来的には「月面基地の電力供給源」としても期待されている。
NASAエンジニアのカーク・ソレンセンはこう語る。
「理論上、手のひらに乗る量のトリウムで、一生分の電力をまかなえる。しかもそれは、地球だけでなく、月でも可能だ。」
小さな一歩、大きな変化へ
― 2メガワットの成功が示す希望
今回中国が稼働させた原子炉は、わずか2メガワットの熱出力。MITが持つ研究炉(6メガワット)よりも小さい。
だが、世界初の「連続稼働しながら新たな燃料を補充する」という実証に成功した点は、技術史的に画期的だ。
中国はすでに、2030年までに60メガワット級の本格炉の運転を予定している。さらに、スイスでは2026年にコペンハーゲン・アトミクスがトリウム炉の試験稼働を計画中だ。
インドも世界最大のトリウム埋蔵国として研究を続けており、アメリカでも複数のスタートアップが再びトリウム炉の開発に乗り出している。
最後に:この一歩をどう受け止めるか?
トリウムは、技術としてはすでに現実となりつつある。しかしその実用化は、20〜30年という長期的な覚悟と粘り強い投資を要する。
中国トリウム炉プロジェクトのリーダー・朱宏氏はこう語る。
「この分野で意味ある成果を出すには、20年、30年という人生の一部を捧げる覚悟が必要です。」
この言葉は、まさにすべてを物語っている。
トリウムは果たして、次世代エネルギーの救世主か?
それとも「高尚な夢」で終わるのか?
私たちはいま、その分岐点に立っているのかもしれない。
当サイトイチオシVPNは、NordVPN!
その理由・・
その1 「本当にVPNに接続しているのか?」と2度見するほど、快適・快速
その2 「赤ちゃんでも使える、ワンクリックVPN接続」
その3 「あなたも、今日からハッカーデビュー」使い切れないほど、セキュリティ機能が満載!ダブルVPNって誰が使うの?!
・
・・
その99 日本向のVPNのサーバが91台と他社とくらべてダントツ多い。
とりあえず、今年はこれ一本で間違いなし。











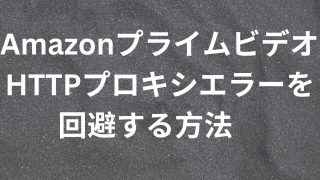



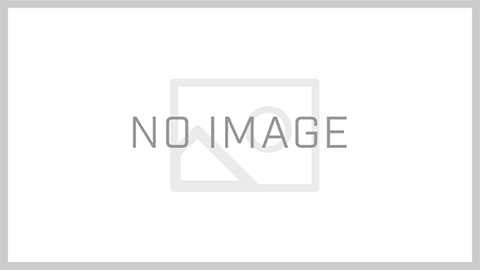
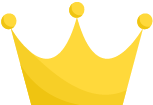 No1. Surfshark/サーフシャーク
No1. Surfshark/サーフシャーク
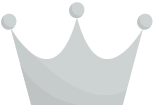 No2. Smart DNS Proxy
No2. Smart DNS Proxy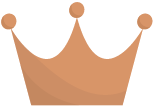 NordVPN
NordVPN